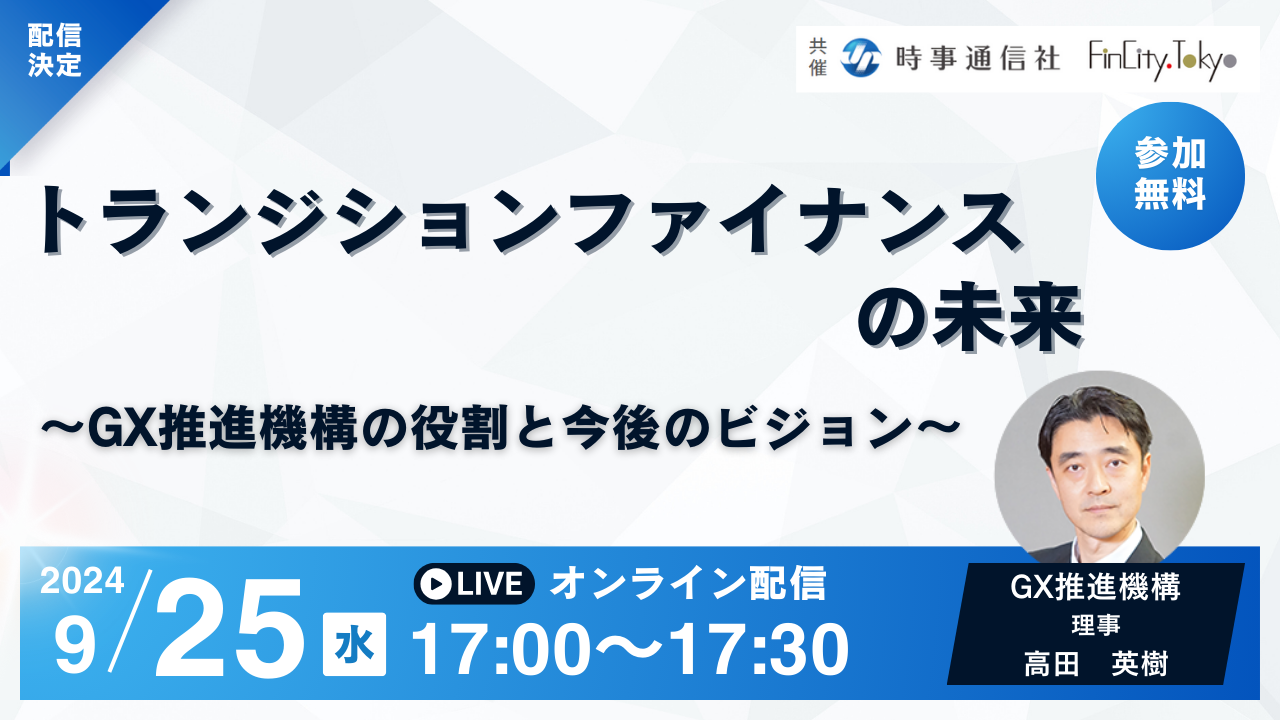2024年08月02日
金融教育とは?
義務化された背景や授業の進め方

現在において、お金や資産形成といった経済・金融と関わっていくことは避けられません。
2022年4月には、高等学校の学習指導要領の改定により、「金融教育」の拡充が決定し、各学校段階の教育現場でも金融教育が取り入れられています。
この記事では、金融教育の定義や目的、義務化の背景などについて詳しく解説します。
目次
金融教育(金融経済教育)の定義
金融教育の支援を行う金融広報中央委員会では、金融教育を「お金や金融のさまざまな働きを理解し、それを通じて自分の暮らしや社会について深く考え、自分の生き方や価値観を磨きながら、より豊かな生活やより良い社会づくりに向けて、主体的に行動できる態度を養う教育」
(金融広報中央委員会公式HP「金融教育の狙いと基本的性格」)と定義しています。
学校教育全体を通じて「生きる力」、すなわち自ら学び、自ら考え、主体的に判断・行動していく力を養うことは重要なテーマです。金融教育は、生活する上で不可欠なお金をテーマとして、より具体的に生活や物事を具体的に理解できるものです。現実に即した知識の習得や、工夫・判断・行動する力を養うことができる点で有効な教育手段だとされています。
金融教育の目的
金融教育の目的には、大きく分けて以下の2つがあるとされています。
個人と社会全体にとって極めて重要な役割を果たし、持続可能な経済成長に寄与します。
- 自立する力を身につける
- 社会と関わる力を身につける
自立する力を身につける
1つ目の目的は、自立する力を身につけることです。経済的に自立するためには、働いて収入を得ることが欠かせません。収入を得るというテーマを通じて、働くことの意義や楽しさ、辛さなどを理解してもらうことで、なりたい自分やより良い生き方について考え、主体的に職業を選択し働く力を身につけます。
また、使えるお金が有限であることを理解した上で、貯蓄や消費にどのように振り向けるのか、どう工夫してやりくりするか、生活していく上でどのようなリスクがあるのかなどについて身をもって理解できます。
これらの理解や体験を通じて、将来を見通し、より豊かな生き方を主体的に考え、努力していく「自立する力」を養うことが、金融教育の大きな目的です。
社会と関わる力を身に着ける
2つ目の目的は、自立する力を身につけることです。経済的に自立するためには、働いて収入を得ることが欠かせません。収入を得るというテーマを通じて、働くことの意義や楽しさ、辛さなどを理解してもらうことで、なりたい自分やより良い生き方について考え、主体的に職業を選択し働く力を身につけます。
また、使えるお金が有限であることを理解した上で、貯蓄や消費にどのように振り向けるのか、どう工夫してやりくりするか、生活していく上でどのようなリスクがあるのかなどについて身をもって理解できます。
これらの理解や体験を通じて、将来を見通し、より豊かな生き方を主体的に考え、努力していく「自立する力」を養うことが、金融教育の大きな目的です。
社会と関わる力を身に着ける
2つ目の目的は、社会と関わる力を身につけることです。金融や経済の仕組みを理解することで、社会と自分とのつながりや自分の行動が社会にどう影響していくのかを自覚できるようになります。
たとえば、働くということは単にお金を得るということではなく、働くことを通じて社会やサービスを受ける人たちの役に立つことであると、職場体験などで身をもって知ることで、社会との関わり、ルールなどを体感的に理解できます。
これらの体験や理解を通じて、自分が社会の一員であることを実感し、より良い社会を築くためにどうするべきなのかなど、社会に対して幅広く関心をもち、主体的に判断・行動できる力を養うことも、金融教育の大きな目的です。
金融教育が義務化された背景
- 金融トラブルを防止するため
- 老後資金を確保するため
- 諸外国よりも金融教育が遅れているため
それぞれについて詳しく解説
自立する力を身につける
1つ目の目的は、自立する力を身につけることです。経済的に自立するためには、働いて収入を得ることが欠かせません。収入を得るというテーマを通じて、働くことの意義や楽しさ、辛さなどを理解してもらうことで、なりたい自分やより良い生き方について考え、主体的に職業を選択し働く力を身につけます。
18歳といえば、高校生・大学生の人が多く社会経験もまだまだ少ないのが現実です。加えて、インターネットやSNSの普及により、情報商材や健康食品の購入トラブルなど、若年層のトラブルが増えています。
成年年齢となると、これらの契約も自己判断とみなされ、取り消しもできなくなるため、トラブルを避けるためにも、若いうちから金融に関する知識を身につけておくことが必要になっています。
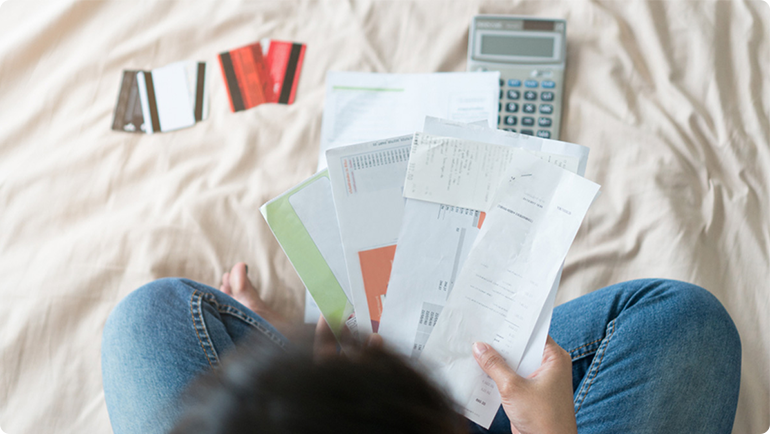
老後資金を確保するため
2つ目の背景は、老後資金を確保するためです。近年の少子高齢化により、日本の公的年金の財政状況は悪化しており、老後の生活を年金だけで支えるのは難しくなっています。加えて、日本は超低金利の状態が続いており、この状態が継続すれば貯蓄だけでは資産はほとんど増えません。
このような現状を受け、老後資金をはじめとした将来的に必要となるお金を長期的な目線で資産形成していく必要があります。金融教育では、投資については範囲とされており、若いうちから資産形成の手法やリスクなどを身につけていくことが重要です。
このような現状を受け、老後資金をはじめとした将来的に必要となるお金を長期的な目線で資産形成していく必要があります。金融教育では、投資については範囲とされており、若いうちから資産形成の手法やリスクなどを身につけていくことが重要です。
諸外国よりも金融教育が遅れているため
3つ目の背景は、諸外国よりも金融教育が遅れていることです。2019年に金融広報中央委員会が行った「金融リテラシー調査」によると、日本では学校での金融教育を受ける機会がなかった人が75%、家庭での機会がなかった人が62%といずれも、金融教育の機会の少なさが目立つ結果となりました。加えて、金融知識に関する正誤問題の正当率も先進諸国の中で最も低い結果になっています。
これらの結果から、日本の金融教育は諸外国に後れをとっている状況を改善するためにも、金融教育の義務化の必要性が高まっている理由でしょう。
金融教育の授業の進め方
金融広報中央委員会が作成した金融教育プログラムでは、金融教育プログラムでは、高校卒業までに学習すべき金融教育の分野を、以下の4つに分類しています。
また、これらの分野について成長段階に応じて学んでいけるよう金融教育プログラムでは、各段階で学ぶことを定義しています。
- 生活設計・家計管理に関する分野
- 金融や経済の仕組みに関する分野
- 消費生活・金融トラブル防止に関する分野
- キャリア教育に関する分野
ここでは、各学校段階での金融教育の目的や
内容について詳しくみていきましょう
小学校
小学校では、低学年では物やお金の大切さ、ものやサービスの利用の対価としてのお金の役割、払い方についての学習が主体です。
中学年になると、欲しい物と必要なものの区別の仕方やこづかい帳などを活用したお金の管理、預金すると利子がつくことなどを学習します。
高学年では、生活に関わるさまざまなお金の働き、預金や貸付などの銀行の機能について学び、加えて経済把握や経済変動、経済政策、社会保障の存在など、金融にまつわる社会の仕組みといったものも対象です。

中学校
中学校では、家計の収入と支出、カードなどの見えないお金の使い方やリスクなど、より高度な経済活動や市場の仕組みなどを学んでいきます。
金利などの仕組みについても理解を深め、貯蓄や運用によるメリット・デメリットを把握することで、自身で将来に向けた資産形成に取り組む姿勢を身に着けます。
また、生活設計の必要性やローンの仕組みやリスク、為替の原理などについての学習も加わり、より経済的に自立するための金融知識の習得につながっていくのです。学校によっては、修学旅行などの機会を通じて、学んだ知識を活用した収支管理の実践を行う取り組みなどを行う場合もあります。
高校
高校の金融教育では、より高度な生活設計の重要性や社会的責任について学び、社会人として自立するための能力を養います。
主な学習内容は、以下のようなものです。
- 電子マネーや地域通貨などの理解
- 決済機能の多様化など現代社会の仕組みについての理解
- 預金、株式、債権、投資信託、保険等の基本的な金融商品の特徴
- 住宅ローンや貸与型奨学金の仕組み
- 金融商品についてのリスクとリターンの関係と分散投資などのリスク管理方法
- 生涯収入や支出を理解し、生活設計を立てる
- 年金や社会保障制度の仕組みや役割の理解
上記のように、高校での学習内容は幅広い分野にわたって、高度な知識を学びます。資産形成や収入と支出のコントロールなど、生活におけるさまざまな場面で、より良い判断・行動ができる人格形成を目指すことが主題です。
大学
大学では成年年齢となり、社会人として自立するための能力を確率するための教育が行われます。
大学卒業後の具体的なライフプランの設計や、金融商品のリスクとリターンについてもより具体的に学びます。
また、家計管理の分野の目標は、収支管理の必要性やアルバイトなどの収支改善の方法、計画的な支出・投資が行えるようになることです。
まとめ
金融教育は、成年年齢の低年齢化、電子マネーなど貨幣の多様化、公的年金の財政悪化など、若年層にとっても、金融知識は非常に重要なものとなっています。
ここまでご説明したとおり、金融教育とはお金や投資に関する仕組みを学ぶことではありません。生活を取り巻く金融や経済の仕組み、リスクなどを幅広く理解することで、より自立した生活設計力や判断力などの「生きる力」を養うこと役割です。
学校教育の現場でも、金融プログラムが整備されていますので、これらを活用し、子どもたちの「生きる力」の育成に継続的に取り組んでいきましょう。