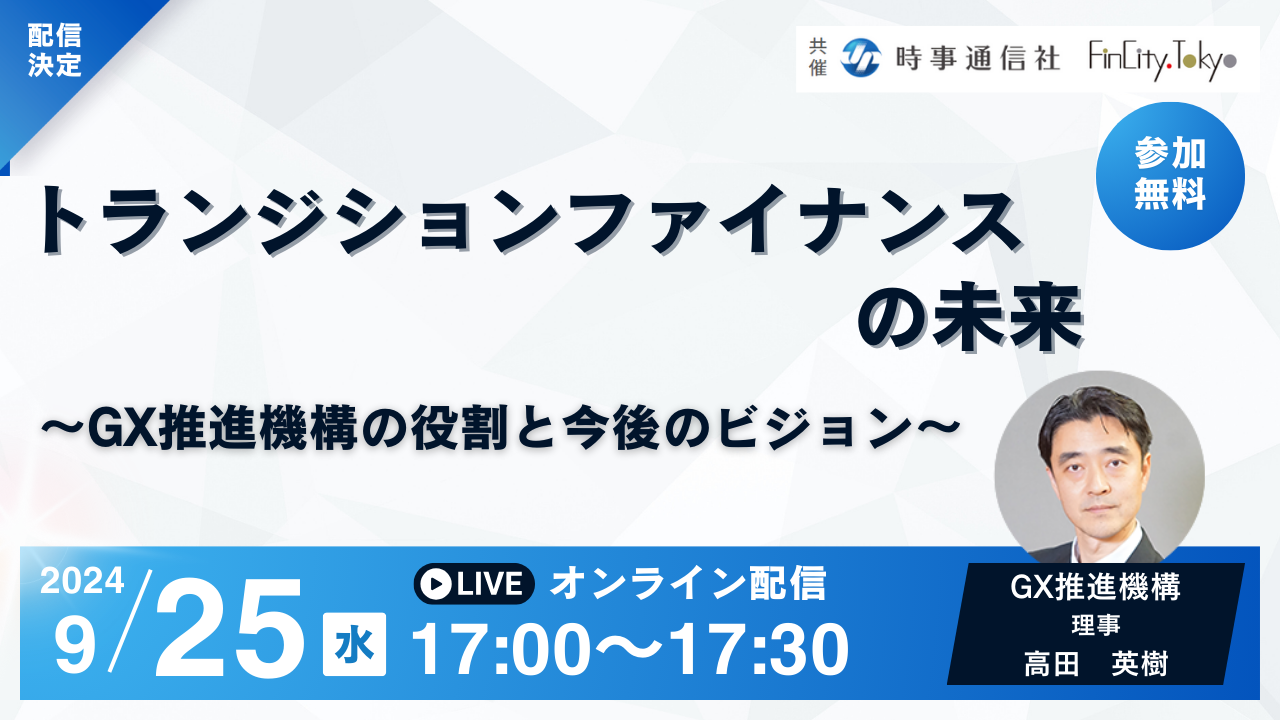2024年08月09日
学校だけじゃない!
家庭でも金融教育を学ぶべき理由と教え方とは?

「学校で金融教育が始まっているけど、家庭でも取り組むほうがよいの?」などの疑問を抱いていませんか。どのように向き合えばよいかわからず困っている方は多いでしょう。
結論から述べると、家庭でもできることを行うほうがよいかもしれません。少し工夫するだけで、日常生活の中でもさまざまな金融教育を行えます。ここでは、家庭における金融教育の必要性と具体的な取り組みなどを解説しています。金融教育に興味がある方は参考にしてください。
目次
家庭でも金融教育(金融経済教育)を学ぶべき理由
生活環境の変化や経済社会環境の変化を受けて、子どもたちに対する金融教育(金融経済教育)の必要性が高まっています。2022年4月から高校で金融教育が必修化されるなど、学習環境は整いつつありますが、それでも十分とはいえません。
金融経済教育を推進する研究会が実施した調査によると「金融経済教育を授業で取り扱う際に、難しいと感じていることはありますか。」との問いに対して、49%の教員が「教える側の専門知識が不足している」と回答しています。授業時間について、44.1%の教員が足りない(やや足りない38.3%、まったく足りない5.8%)と回答している点も見逃せません。学習指導の課題として、52.3%の教員が「用語・制度の解説が中心となってしまい、実生活とのつながりを感じにくい」、44.4%の教員が「金利や金融商品の種類、リスクとリターンの関係など、実践的な知識が少ない」と回答している点もポイントです。[1]
同調査から、さまざまな課題を抱えながら金融教育を行っていることがうかがえます。不足を感じる場合は、家庭でも金融教育を行う必要があるでしょう。
金融教育の性格にも注意が必要です。金融教育は、生きる力、自立する力の育成と言い換えられます。このような力の育成には、家庭での教育が欠かせません。例えば、金銭感覚などは、家庭教育の影響が大きいと考えられます。学校教育の有無に関わらず、家庭でも金融教育に取り組んでみてはいかがでしょうか。
家庭で金銭教育を行うメリット

家庭で金融教育を行う主なメリットとして以下の2点があげられます。
好きなタイミングで開始できる
家庭での金融教育は、子どもの年齢を問わず始められます。子どもがお金に興味をもったタイミングや保護者が考えるベストなタイミングで金融教育をスタートできる点は魅力です。例えば、おこづかい制を導入したタイミングで金融教育を始めるなどが考えられます。
子どもの成長に合わせて教育内容を変更できる点も魅力です。子どもが小さい間はおこづかい管理を通して金銭感覚を身に着けさせる、子どもが成長してからは金融商品を通して資産運用を学ばせるなどが考えられます。家庭の方針にあわせて柔軟な金融教育を行えます。
親も一緒に学習できる
家庭で金融教育を行う場合、保護者も金融の知識を深められます。子どもに教育するため、一定の知識を求められるからです。子どもと一緒に学びながら金融の知識を深めることもできます。例えば、子どもと議論しながら目的に合っている金融商品を探す、資産の運用方針を決定するなどが考えられます。子どもとの買い物を通して、自身の金銭感覚を見直すこともできるでしょう。保護者にとっても有意義な時間になるはずです。
家庭で金融教育を行う注意点
家庭で金融教育を行うときは以下の点に注意が必要です。
お金に対してネガティブなイメージをもたせない
保護者が意識していなくても、日常生活を通してお金について学んでいる子どもは少なくありません。何気ない発言や行動から影響を受けているケースは多いでしょう。
子どもがお金に対してネガティブなイメージを抱かないように日ごろから保護者は注意しなければなりません。ネガティブなイメージを抱くと、金融教育に対して後ろ向きになる恐れがあります。
例えば「投資をすると必ず損をする」のように、一側面だけを教えると投資は怖いものと理解するようになるでしょう。
「損をすることもあるが、知識を身に付ければリスクをコントロールできる」などのように、先入観を排除して教育を行うことが大切です。
一度にたくさんのことを教えない
子どもの興味や成長に合わせて金融教育を行うことも重要です。一度にたくさんのことを教えると、混乱してしまう恐れや金融に苦手意識をもつ恐れがあります。
いつ頃、何を教えればよいかわからない場合は、知るぽると金融広報中央員会が発表している「金融教育プログラム 学校における金融教育の年齢層別目標」を参考にするとよいかもしれません。
「A生活設計・家計管理に関する分野」「B金融や経済の仕組みに関する分野」「C消費生活・金融トラブル防止に関する分野」「Dキャリア教育に関する分野」にわけて年齢層別(小学生低学年・中学年・高学年、中学生、高校生)の目標が示されています。[2]
家庭でできる金融教育

家庭で金融教育を行いたいものの、具体的に何を行えばよいかわからない方は多いでしょう。ここからは、家庭でできる金融教育を紹介します。
おこづかいを適切に管理させる
身近な金融教育としてあげられるのが、子どもにおこづかいの管理を任せることです。子どもが小さいと「まだ早い」と感じるかもしれませんが、失敗を通して管理能力を育むこともできます。
例えば、おこづかい日に全額を使い切って、翌日以降、欲しいものを買えなくなると、次からは計画的に使うことを考えるでしょう。欲しいものを購入するため、我慢をしてお金を貯めることを覚えるかもしれません。大切なポイントは、必要以上に口を出さないことです。
一緒に買い物に出かける
子どもと一緒に買い物へ出かけることも金融教育になりえます。ポイントは、買い物中の会話を通して金銭感覚を養うことです。
会話の例として「洗剤の残りが少なくなったから新しいものを購入する」「商品Aよりも安いから商品Bを購入する」などが考えられます。
これらの会話を通して、買い物をするタイミングや商品選びの基準などを子どもは学ぶでしょう。一般的に、子どもの金銭感覚は保護者から大きな影響を受けると考えられています。買い物中の何気ない会話も大切にするべきといえます。
家庭内で仕事の話をする
保護者の仕事の話も、金融教育に活用できます。仕事とお金の関わりや仕事と社会の関わりなどを学べるからです。
保護者の仕事の話をきっかけに、なりたい職業を見つけたり経済に興味をもったりすることも考えられます。どのような仕事をしているか、どのような会社と取引があるか、なぜお金を稼げているかなどを自然な流れで話してみるとよいでしょう。
ただし、ネガティブな話をすると、仕事に対して後ろ向きになる恐れがあります。前向きになれるような話をすることが大切です。
ゲームを通じて金銭感覚を養う
楽しみながら学べると、子どもは積極的になります。前向きに学んでほしい場合は、ゲームを通じて金銭感覚を養うとよいでしょう。
具体的には、お金の仕組みや投資の基本などを学べるボードゲーム・カードゲーム・ゲームアプリなどの活用が考えられます。小学校低学年から利用できるものもあります。
子どもを惹きつけたい場合は、これらの活用を検討してみてはいかがでしょうか。
まとめ
金融教育は社会の中で生きる力を育てる教育です。高校で必須化されるなど、学習環境は整いつつありますが、現状では「教える側の専門知識が不足している」などの課題も抱えています。以上を踏まえると、家庭でも取り組むほうがよいかもしれません。具体的な取り組みとして、子どもにおこづかいを管理させる、家庭内で仕事の話をするなどが考えられます。子どもの興味や成長に合わせて、前向きに取り組めるように働きかけることが大切です。
[1]出典:金融経済教育を推進する研究会
「中学校(教員・生徒)における金融経済教育の実態調査報告書」
[2]出典:知るぽると 金融広報中央委員会
「金融教育プログラム 学校における金融教育の年齢層別目標」