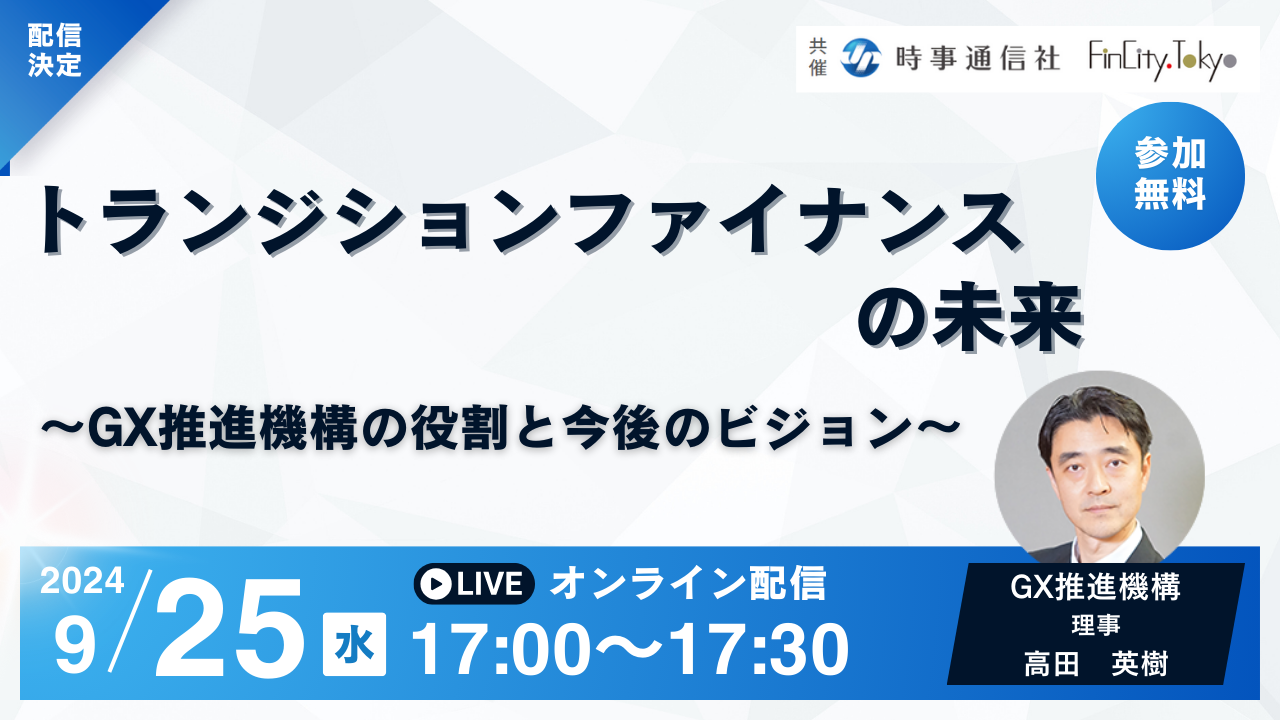2024年08月09日
中学生に対する金融教育で教える内容とは?
必要性についても解説

2022年4月から、高校で金融教育が必修となるなど、教育課程に合わせた金融教育の必要性はどんどんと高まっています。中学校でも以前から金融教育は実施されていましたが、より具体的な教育が望まれています。
この記事では中学生に対する金融教育の内容やその必要性、学習の実践事例などについて、詳しく見ていきましょう。
目次
中学生に対する金融教育(金融経済教育)の内容
中学生に対する金融教育(金融経済教育)は、主に「技術・家庭科」「社会科」の授業内で実施されます。中学生が学ぶべき分野として、以下の4つに分け学習を進めます。
- 生活設計・家計管理に関する分野
- 金融や経済の仕組みに関する分野
- 消費生活・金融トラブル防止に関する分野
- キャリア教育に関する分野
「生活設計・家計管理に関する分野」では、お金やサービスに限りがあることや、資金管理の必要性、家計の収入・支出を管理する方法を実践的な収支管理などを通じて学びます。また、貯蓄や運用の方法やさまざまな金融商品、リスクとリターンの関係、社会保障やローン、金利計算など、より将来の生活設計に必要な金融の仕組みについても、対象です。
「金融や経済の仕組みに関する分野」では、金融機関の種類や機能、間接金融・直接金融の仕組み、起業、クレジットカードやキャッシュレス決済などが、学習項目です。社会保障や公共サービス、景気や物価変動、為替など、経済全体の動きや働きがどのように自分たちの生活に関わっているのかといった、比較的社会性の高い学習内容となっているのが特徴といえるでしょう。
「消費生活・金融トラブル防止に関する分野」では、消費者の権利や責任、売買契約の仕組みなど、消費者として身に付けておくべき基礎的な知識を学びます。また、クレジットカードやローンなどの使用上の留意点、インターネットなどでのトラブル事例、悪徳商法や詐欺的商法の見分け方など、将来のトラブルに備えて対処方法や回避方法なども対象です。
「キャリア教育に関する分野」では、働いて収入を得ることの重要性ややりがい、社会的な価値について考える機会を設け、将来の夢や希望を持ち、努力する姿勢を身に付けます。また、労働者の権利と義務、起業の意義などについても学ぶなど、働くことの意義や権利、社会との関わりなどについて自分ごととして捉える内容が増えるのも中学校での教育の特徴です。
このように中学校での金融教育は、自分のおこづかいの範囲だけでなく、社会全体の金融の仕組みや家計全体まで学習範囲が広がり、自分の将来の生活設計や職業選択できるようになるための学習となっています。
中学生が金融教育を受ける必要性
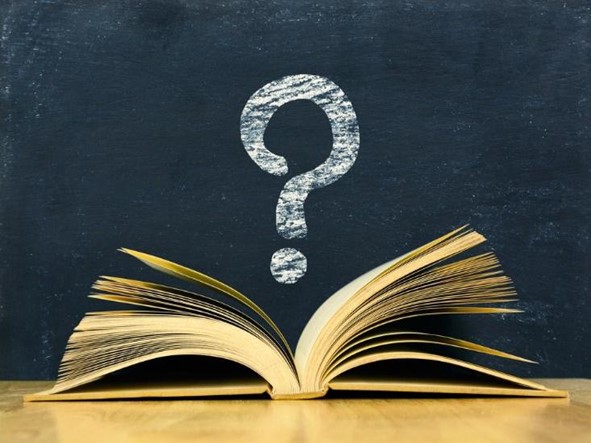
では次に中学生が金融教育を受ける必要性について、以下の3つのポイントから詳しく見ていきましょう。
- 複雑化した金融の仕組みに対応する
- 資産形成の知識を身につける
- おこづかい以上の範囲について考え始める
複雑化した金融の仕組みに対応する
現代の金融の仕組みは、クレジットカードやキャッシュレス決済、インターネットを通じた契約など、技術の進化に合わせて複雑化しています。子どもたちは現金に触れる機会も少なくなり、労働と収入の関係性や働くことの価値、生活にお金がかかっていることの実感も得にくくなっています。
このように複雑化した金融の仕組みを家庭学習だけで補うのは、かなり難しいのが現状です。また、成年年齢が18歳に引き下げられたことで、高校卒業時には自らの判断だけでクレジットカードを作成できたり、ローンの契約ができたりしてしまいます。
金融に関する知識がない状態では、さまざまなトラブルに巻き込まれるケースや、家計管理ができず生活が成り立たなくなることも考えられます。
金融教育を早期にスタートし、正しい金融知識を身につけていくことは、より経済的に豊かで安定した生活を送るためにも必要不可欠となっているといえるでしょう。
資産形成の知識を身につける
近年の少子高齢化に伴い、日本の社会保障制度は不安定な状況にあり、将来的には公的年金だけでは生活が成り立たなくなる可能性が高くなっています。また、超低金利時代の継続により貯蓄だけでは資産が増やせなくなっており、老後に安定した生活を送るためには、若いうちから資産を運用し、資産形成をしておくことが大切です。
しかし一方で、金融商品は多様化・複雑化しており、金融リテラシーがない状態で資産を運用すると、大きな損失を被る可能性もあります。個人が自分の判断で適切なリスクを取りながら、長期的な目線で資産形成を行うためにも、若いうちに金融リテラシーを身につけておくことが必要になっているのです。
おこづかい以上の範囲について考え始める
中学生ともなるとおこづかいの額や使い道の自由度も、小学生に比べてかなり広くなっているでしょう。また、スマートフォンを持つようになるなど、家計に関連する支出も増えていきます。
さらに現代ではインターネットでの商品・サービスの購入で容易に欲しいものが手に入れられてしまう環境にあることで、思わぬ浪費で家計を圧迫してしまうといったケースも見られます。
そのため、中学生という成長段階に合わせ、自分のおこづかいの範囲だけでなく、家計全体の収入や支出など、小学生よりもより広い範囲で家計管理について考え、自ら関わっていく姿勢が大切になってきます。金融教育を通じて、社会や家庭などより広くお金に関連する視野や知識を身につけていくことが重要になっている点も金融教育が必要になっている理由の1つです。
中学生が受ける金融教育の実践事例

では最後に中学生が受ける金融教育の実践事例について、金融教育が取り扱われることが多い以下の3科目に分けてご紹介します。
- 社会科
- 数学科
- 技術・家庭科
社会科
社会科では、家計のシミュレーションなどを通じ、身近な消費生活や経済活動の意義について考え、理解・関心を高めることなどが目的です。
実践事例として紹介されているのは「家計と商談のシミュレーションゲーム」という内容で、将来自分が独立した家計を営むと想定して、家計や経済に関する幅広い知識や考え方を実践形式で学びます。
このプログラムでは住居のローンや毎月の食費・光熱費などの生活費、子どもの教育費や保険、預貯金額など、より長期的かつ幅広い範囲が対象です。また、住居や自動車など大きなお金を使用するライフイベント時の行動などについてもシミュレーションすることで、将来的にしっかりとした家計管理ができる能力を育てます。
数学科
数学科では、日常生活の中で必要な携帯電話費用を用いて、一次関数などの数学的思考や理解を進めることで、数学的知識を日常生活で利用する素養を育てます。
実践事例として紹介されているのは「携帯電話の一番お得なプランを選ぼう」という内容で、日常で多くの人が利用する携帯電話のプランについて、どのプランを選択するかを考えます。
日常生活にあるものを活用することで、金銭に関する健全な感覚を養うとともに、身の回りの事象を数学的に捉え、知識を活用できる能力が育てられます。
また、実践事例ではお得なプランをただ導き出すだけでなく、事前にどのプランがお得なのか予想する、1人で考えたあとにグループでディスカッションするなど、より思考過程を分け、自ら判断する能力や得た情報や意見を活用する能力の育成にも役立つでしょう。
技術・家庭科
技術・家庭科では、消費者としてのロールプレイングを通じて、消費生活に必要な知識やルールを身に付け、適切な選択、購入ができる能力を育てます。
実践事例として紹介されているのは「賢い消費者になろう ロールプレイング」という内容で、消費者として商品を購入するというプロセスを通じ、数多く存在する販売方法のメリット・デメリットや、より自分の状況にあった消費活動とはどういったものかについて考えます。
また、消費者の権利や義務、悪徳商法などのトラブルの事例、環境にも配慮した消費活動についても学びます。店舗販売や無店舗販売などの販売形式ごとに利点や問題点をあげ、ロールプレイングを行うことで、販売方法についての知識を深め、自分にあった購入方法を選ぶことができるようになります。
それ以外にも、消費者の権利や義務、契約についても具体的に学び、将来発生する可能性のあるトラブルなどへの対処法や予防方法を身につけられます。
金融や消費トラブルがますます若年化していく可能性もあることから、実際の消費行動を通じて基本的な知識を身につけておくことは非常に重要だといえます。
まとめ
今回の記事では、中学生の金融教育の内容やその必要性、学習の実践事例などについて詳しくご紹介しました。
中学生になるとおこづかいの金額も増え、欲しいものに高額なものも出てくるなど、より家計に影響があることも増えてきます。行動範囲が増えることで、金融トラブルに巻き込まれる可能性も増えてくる可能性があるでしょう。
これらの状況も踏まえ、小学生よりもより範囲を広げ、家計全体や金融・経済社会全体についても学習する内容になっています。