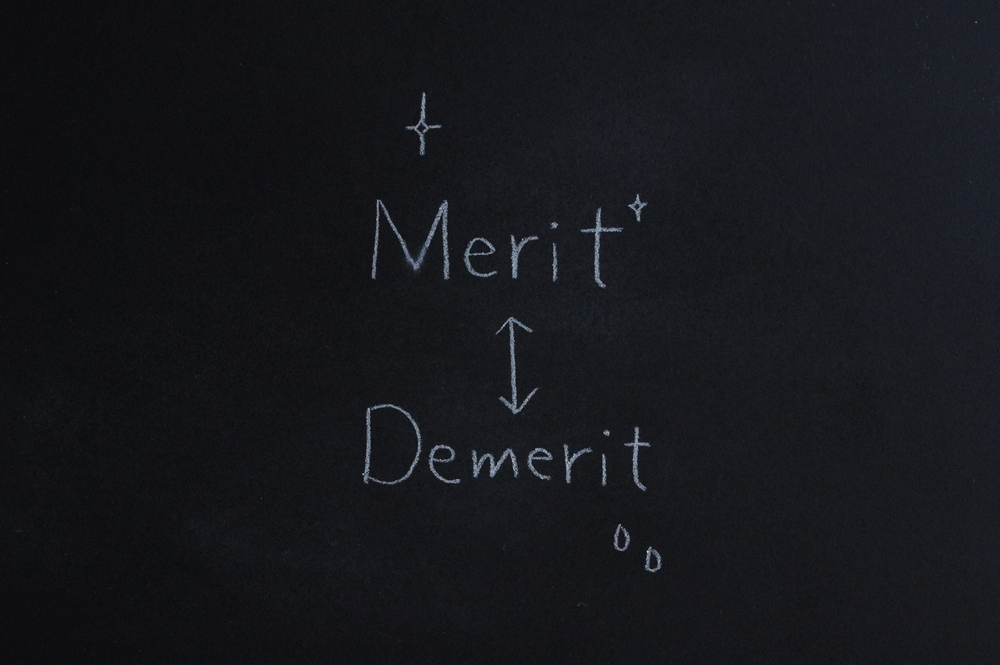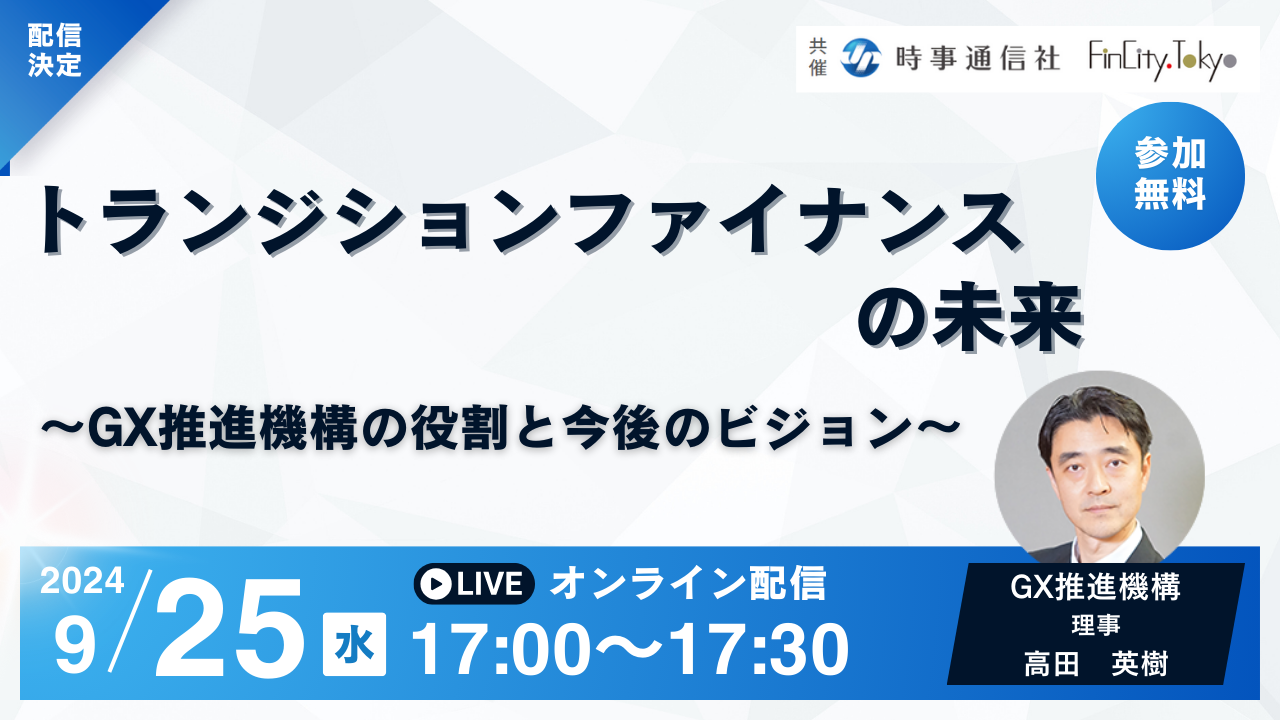2024年08月08日
日本の金融教育の現状と課題は何か?
データから紐解いて解説

日本における金融教育(金融経済教育)は、金融広報委員会が「金融教育元年」と位置づけた2005年より取り組みが始まり、2022年からは学習指導要領の改訂により、高校での金融教育が義務化されました。
一方で金融教育の現場では教員の金融リテラシーのばらつきなど課題も散見されています。
そこでこの記事では、日本の金融教育の現状と教育の課題などについて詳しく解説します。
目次
日本の金融教育(金融経済教育)の現状
まずは、日本の今の金融教育の現状について見ていきます。日本の金融教育の現状を推し量るため、2022年に金融広報中央委員会が実施した「金融リテラシー調査」を参照してみましょう。
同調査では学校において金融教育を行うべきとの意見は71.8%と高い水準にある一方で、「金融教育を受けた」と認識している人は、そのうち7.9%にとどまります。
学校での金融教育の機会や経験を調査したアンケートでも「受ける機会があり受けた」人は7.1%にとどまり、学生世代(18~24歳)に絞っても18.4%と低い水準です。
金融広報中央委員会が「金融教育元年」と位置づけた2005年以降、金融教育に関わる教育の拡充に関する取り組みが行われていたことから、若年層の教育機会は徐々に増加しているものの、米国全体の同調査結果が20%であることを見ても、まだまだ低い水準であることがわかります。
また、金融教育を担う教員についても「学校での教育機会があり受けた」とする人の割合は8.2%と低いことも注目すべき点です。
2022年の学習指導要領の改訂により高校での金融教育が義務化されましたが、生徒への教育を担う教員のリテラシーの向上をどのように図るかは重要な課題となっていきそうです。
もうひとつの参考として、株式会社QUICKが発表した「高等学校における金融教育の意識調査2022」を見てみましょう。同調査は、金融教育義務化により開始した教育現場の実態を調査したものです。
「どのような形式で授業を実施したか」という質問では座学中心での実施に回答が集まる一方で、「どのような形式での授業が好ましいか」という質問では、外部講師の講演、学校外の施設見学が高い水準にあるなど、ギャップがあることがわかります。
とくにこの傾向は資産形成・運用のテーマにおいて顕著であり、金融教育を受けたことのない教員による指導の難しさが表れているのかもしれません。
また金融教育に関して生徒が関心・興味を持っていたかの調査では、教員の金融教育への意欲の有無、学校側の積極性の有無で、関心度に大きな差が出ています。
これらの調査結果からも、今後の金融教育のさらなる充実に向けては、それを担う学校や教員の金融リテラシーの向上、教育環境の整備が必要になっていくといえるでしょう。
日本の金融教育の課題

日本の金融教育は義務化から日も浅く、まだまださまざまな課題を抱えています。ここでは日本の金融教育の課題を以下の3つのポイントから見ていきましょう。
- 教員側の専門知識が不足している
- 授業時間を確保できない
- 授業内容が難しい
教員側の専門知識が不足している
1つ目の課題は、教員側の専門知識が不足していることです。さきほどご紹介した「金融リテラシー調査」でも、教員の中でも金融教育を受けたと認識しているのはわずか8.2%にとどまっています。金融教育を受けた経験がないため、教育に必要な金融リテラシーや経験が不足しています。
加えて、高校における金融教育は家庭科・公共科のカリキュラムの中に織り込まれていますが、いずれの担当教員においても、これまでの授業範囲外の教育を担う必要があり、新たな知識の習得が不可欠になります。
これらのことから、専門的な知識の不足に不安を覚える教員も多く、教員側の専門知識の不足は、金融教育における大きな課題といえるでしょう。
授業時間を確保できない
2つ目の課題は、授業時間を確保できない点です。改定された学習指導要領では、金融教育を家庭科・公共科の一部として授業に組み入れる形になっています。
しかし、いずれの科目も英語や数学などといった主要科目に比べると授業コマ数が圧倒的に少なく、多くの時間を金融教育に費やすことは難しいのが現状です。
金融経済教育を推進する研究会が2022年10月に行った「中学校(教員・生徒)における金融経済教育の実態調査報告書」においても、授業時間数が足りないと感じている教員が37.9%もいることからも、時間が不足していることがわかります。
金融教育は学ぶ範囲も広範囲にわたり、体験学習などもその趣旨から重要となることを考えても、授業時間の確保や効率的な教育方法の整備は課題といえるでしょう。
授業内容が難しい
3つ目の課題は、授業内容が難しいことです。金融教育は範囲が広く、経済活動や職業、投資など子どもにとっては馴染みのない複雑な内容にも触れていくものです。
とくに投資・資産形成の分野では、正しい教育ができず誤った理解をすると、その後の生活や判断にも影響を与えることから、授業内容・方法に難しさを感じる教員も多くいます。
前述した株式会社QUICKによる調査においても、好ましい授業形式として、外部講師の講演やゲーム形式での実施が必要と認識しているからも、課題のひとつとして認識しておくべきでしょう。
金融教育のサポート体制

上記の課題を受けて、学校・金融機関などが連携して、徐々にではありますがサポート体制が構築されつつあります。ここでは、現時点で実施されているサポート体制について、以下の点から詳しく解説します。
- 教員研修が実施されている
- 授業の実践事例を確認できる
- 学年別に体験学習を受講できる
教員研修が実施されている
行政や金融機関を中心として、教員向けの研修やセミナーなどが多く実施されています。金融教育の充実化には、それを担う教員の金融リテラシーの向上が欠かせません。
一方で、教員となっている年代の大多数は体系的な金融教育を受けておらず、金融リテラシーにばらつきがある点が課題です。
これを解消すべく、さまざまな行政・民間企業などから教員に向けた研修の機会が設けられています。たとえば、みずほ銀行では教員の金融リテラシー向上に向けた研修や教員の養成支援研究を行っています。
授業の実践事例を確認できる
金融広報中央委員会では「先生のための金融教育セミナー」が実施され、金融教育に取り組んでいる実親事例の紹介や教育内容に」関するワークショップなどが行われています。
授業内容が難しく、うまく子どもに伝えられないことに悩む教員も多く、金融リテラシーの向上と合わせて、具体的な授業の進め方や伝え方が共有されるので、教員の人にはかなり参考になるのではないでしょうか。また、同サイトでは実際に行われた授業の実践事例集も多く掲載されているので、参考にしてみるとよいでしょう。
学年別に体験学習を受講できる
学校での金融教育の支援として、金融機関などが学年別に体験学習カリキュラムを用意していることもあります。みずほ銀行では、小学校から高校までの各年代別に対面・オンラインでの出張授業プログラムが準備されており、各年代で必要な金融教育を体験学習なども交え楽しく学べる内容となっています。
また、民間企業では多くの教員が課題としている投資・資産形成の学習に利用できるゲーム形式の教材の提供などもあります。
これらの教材や支援をうまく活用することで、教員自らの金融リテラシーや教育ノウハウを蓄積しつつ、金融教育の充実を図ることができるので積極的に活用してみてもよいでしょう。
まとめ
高校での導入が義務化された金融教育は、日本においてはまだまだ発展途上の段階にあり、子どもたちのみならず、本来教育する立場にある教員の金融リテラシーの向上も大きな課題となっています。
とくに投資・資産形成については、教員自身が経験のないケースも多く、教育内容やその充実度に不安を持つ教員の方も多くおられます。
一方で、行政や金融機関を中心に金融教育の充実を図るための取り組みは数多く進められており、これらをうまく活用していくことが鍵となるでしょう。