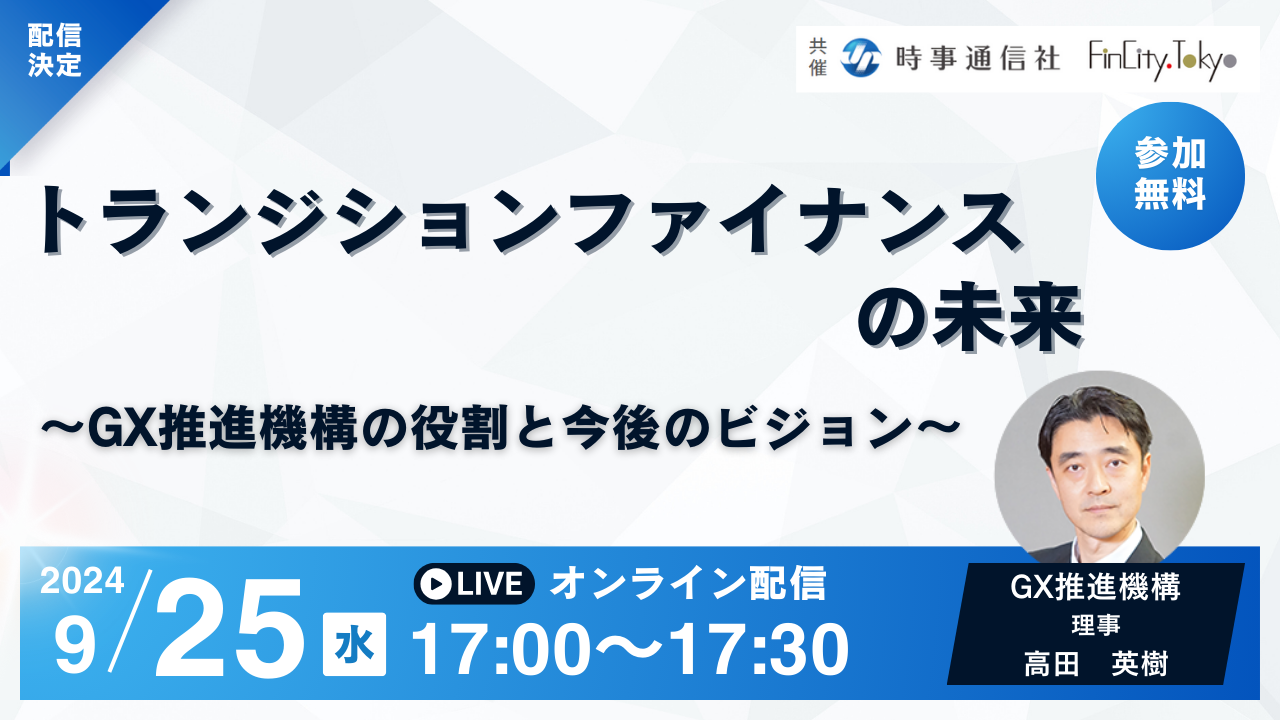2024年08月08日
小学生から金融教育は受けるべき?
必要性や目標を解説

子どもの前ではお金の話をしないという人も少なくありません。しかし、最近では子どものうちから金融教育が取り入れられており、小学校でも年代に応じてお金のことを学ぶ機会が多くなっています。
この記事では、小学生で金融教育を始める必要性や金融教育の実践事例などについて詳しく解説します。
目次
金融教育(金融経済教育)はいつから始めるべきなのか
金融教育(金融経済教育)は、小学生になったころから始めるのがオススメです。これは子どもが自分自身で欲しい物を見つけ、自己主張し始めるのが小学生のころだからです。
お小遣いやお年玉などのお金を手にする機会も増えてくるため、お金に関して最低限の知識を持っておく必要があります。お金が有限であることや、お金を手に入れることが簡単ではないことをこの頃からしっかり教えていくことはとても大切です。
少しずつでいいので、小学生からお金に関して考える機会を与えていくことが、将来お金に関してしっかりと知識を持ち、自立した大人になるための第一歩になります。
小学生に対する金融教育の目標

小学生に対する金融教育の目標は年齢層別に示されており、小学生では「低学年」「中学年」「高学年」の3つの年代に分類されて示されています。小学生という時期は成長や発達が著しいため、学年別に3つに分類されているのが特徴です。
低学年
低学年では、主にお金の基本的な価値や使い方、働くことの大切さなどを学びます。
主な学習内容は以下のとおりです。
- 欲しい物を買うにはお金が必要であることを知る
- お小遣いやお年玉を貯めてみたり、計画的にものを買ったりしてみる
- 硬貨と紙幣の違いを知る
- 家の手伝いや係活動で役立つ喜びをする
中学年
中学年では低学年よりもより生活に近い知識を学びます。「お金を貯めて将来使えるように準備すること」や「使ったお金やもらったお金の記録をつけること」など、より具体的なお金の使い方、管理の仕方を学びます。
また「金融機関の存在」、「銀行に預けると利子がつくこと」など、金融の仕組みについても徐々に学んでいきます。
中学年で学ぶ主な内容は、以下のようなものです。
- 欲しいものと必要なものの区別ができるようになる
- 貯蓄の意義を理解し、計画的に貯蓄する習慣を身につける
- 目的や価格を考えてものを選んで買うことができるようになる
- 金融機関の存在や生産・消費・販売などの生産活動を通じてお金の動きを理解する
高学年
高学年になると金融教育は「社会科」「家庭科」の2つで扱われるようになり、より複雑化・高度化していきます。
社会では国全体の仕組みや社会保障、納税、海外とのお金のやりとりなど、経済の仕組みそのものと自分の生活との関わりなどについて学びます。
家庭科で学ぶ主な内容はプリペイドカードの存在や、計画的な貯蓄、事故や病気に保険で備えることなど、より具体的な家計管理、リスク管理についてです。また、インターネットで起こる金融トラブルなどについても学び、トラブルの予防方法などについても学んでいきます。
小学生が金融教育を受ける必要性
では次に、小学生が金融教育を受ける必要性について、以下の3つのポイントから見ていきましょう。
- お金の使い方を知る
- 将来的に自立する力を身につける
- 現金を目にする機会が減少している
お金の使い方を知る
小学生になると、自分自身で欲しい物を見つけねだることも多くなってきますが、親としてもすべてを与えるわけにはいきません。
小学生から金融教育を行うことで、欲しい物を手に入れるにはお金が必要であり、お金は有限であることを理解させる必要があります。
限られたお金をうまくやりくりして、自分の欲しいものに優先順位をつけるなど、お金の有効な使い方を知るためにも、小学生のうちから金融教育を受けることは非常に有意義なことといえるでしょう。
将来的に自立する力を身につける
将来的に自立する力を身につけられる点も、小学生から金融教育を受ける必要がある理由です。今小学生の子どもたちもいずれは社会人となり、自分で働いてお金を得て生活していかなければなりません。お金の本当の価値ややりくりの方法など、金銭感覚が養われないまま収入を得るようになってしまうと、無駄遣いをして生活が成り立たなくなってしまう可能性もあります。
また、働くことの意義や価値、納税や社会保障などのお金にまつわり社会の仕組みを理解することで、自分が社会の一員となっていることを実感することも大切です。
欲しい物と必要なものを区別できる、労働だけでなく投資や貯蓄の方法を知る、働くことでお金を稼ぐことの価値を知るなど、自立するための基礎的な知識を身につけられる点でも、小学生からの金融教育には大きな意義があるといえます。
現金を目にする機会が減少している
現代ではインターネットでの契約やキャッシュレス決済、口座振替など現金を目にする機会が減少してきていることも、小学生から金融教育を受ける必要がある理由です。
昔は給料日になると親が給料袋を持って帰り、それを使って生活をしていました。必然的に子どもも親がお金を稼いでいてそれで生活できていることのありがたみや、生活にお金が必要であることを目にする、意識する機会も多くあったといえます。
しかし現在では、給料は銀行振込が当たり前で親が働いて給料をもらっていることを意識できる機会は少なくなっています。また、電気代やガス代などの多くは口座振替が主流で、生活するのにお金がかかっていることを意識することは難しいでしょう。
生活にどんなお金がかかっているのか、働かないとお金が稼げないことなどをきちんと説明し、理解させる金融教育は欠かせない状況になっているといえるでしょう。
小学生が受ける金融教育の実践事例

小学生の金融教育では、実際の社会の仕組みなどを活用して、実体験を通じた金融教育を行います。
ここでは、小学生が受ける金融教育の実践事例を「社会科」「生活科」「家庭科」の3つに分けて、金融広報中央委員会が提示している金融教育プログラムから具体的な実践事例をご紹介します。
社会科
社会科では、自分の身の回りの生活に関わるお金の仕組みを利用して、社会が計画的・協力的に進められていることや、そこに必要なお金や社会との関わりについて学びます。
実践事例として紹介されているのは飲料水がどのように確保されているのかを、見学や調査を通じて学ぶプログラムです。このプログラムでは、実際に浄水場を見学したり、学校や家庭の水道料金表を調べたり、ペットボトルを使ってろ過の実験装置を作ったりします。
こういった身近な体験や調査を通じて、飲料水の確保が多くの人の努力や協力によってされていること、飲料水を利用するにはお金が必要であることを学ぶことで、生活を支えている公共サービスの存在や日常生活にもお金が必要なことへの理解を深めます。
生活科
生活科では、パンの購入活動を通じて、限りある予算の中で必要なものを購入することや、消費者としてのマナーなど、社会生活を送る上での基本的な知識やマナーを身につけます。
実践事例として紹介されているのは、パン屋さんなどの自分が住んでいる街の身近な店舗と協力し、実際に購入活動を行うプログラムです。このプログラムでは、実際に店舗を訪れ、数ある商品の中から自分が購入するものを予算の中で計画立てて購入する活動や、店舗の人へのインタビュー活動などを行います。
購入活動を通じて、買い物の計画を立てることや家族や自分が欲しい物を整理し、購入できる能力、買い物をする際のマナーや仕組みについて学びます。
店舗の人へのインタビューを通じて、各店舗の良さや地域との関わりに興味を持ち、愛着を深められる点も目的のひとつです。
家庭科
家庭科では、調理実習や調理実習で使用する食材の購入を通じて、必要な商品を無駄なく購入する力や、品質の良い商品を適正な価格で購入する力を育てます。
実践事例として紹介されているのは「買い物名人になろう」というテーマで、調理実習やそれに使用する食材の購入を行います。このプログラムでは、日常生活によくある買い物を寸劇形式で紹介し、無計画な買い物の問題点や計画的な買い物の必要性について理解します。
また、調理実習で使用する食材の買い物の計画を立てることや、実際に選んで購入する活動を通じて、より適切なものを購入するためにはどんなことが必要かについても学ぶことが可能です。
まとめ
今回の記事では、小学生から金融教育を行う必要性や、小学生での金融教育の目標、実践事例などについて詳しくご紹介しました。
小学生になるとお小遣いやお年玉など、自分のお金を持つことも増え、欲しい物も増えてきます。
お金に関する知識やマナーを日常生活に結びつけて学んでおけば、計画的にお金を使えるようになり、将来自立した生活を送ることにもつながります。
とくに小学生では実体験を通じ、楽しみながらお金や社会の仕組みについて学べる機会を多く作ることで、お金や生活に興味をもたせながら学習を進めることが効果的です。
この記事を参考に、ぜひ小学生のうちから積極的に金融教育を進めてみてはいかがでしょうか。