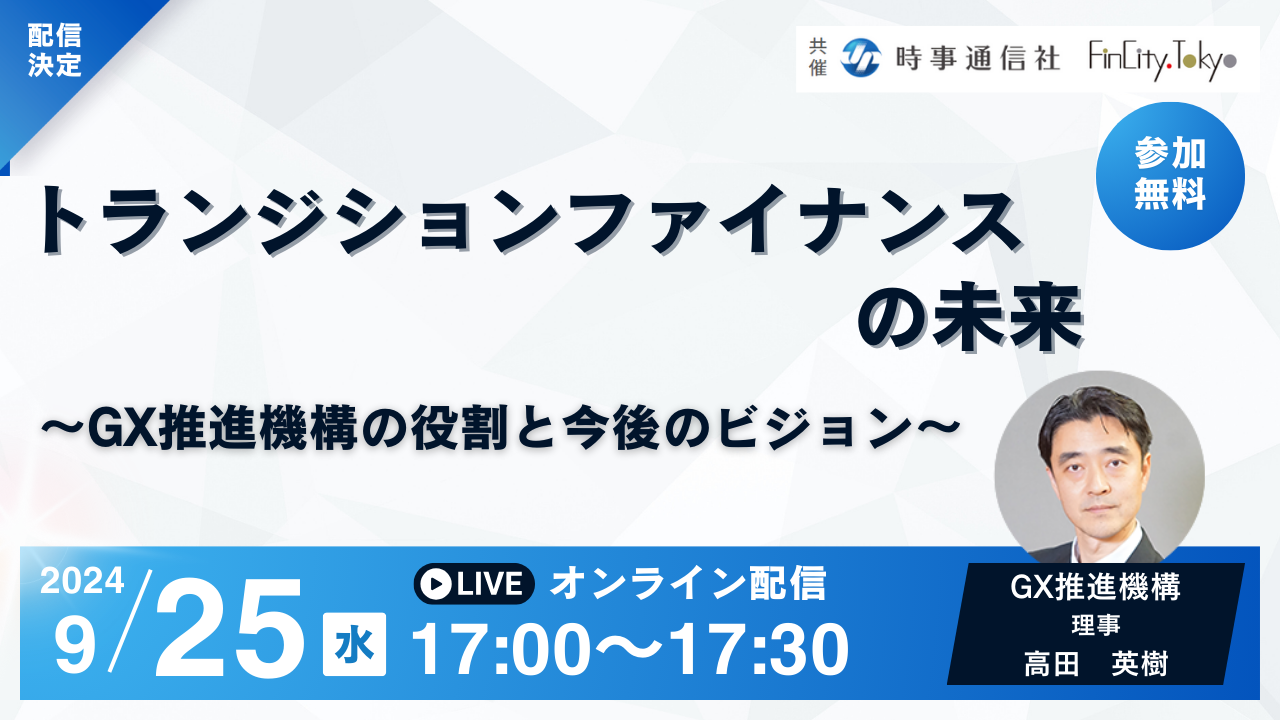2024年08月08日
2022年4月に始まった金融教育の学習内容とは?
項目ごとに解説

2022年4月の学習指導要領改訂に伴い、高校での金融教育が義務化されました。これを受け、金融庁では金融経済教育指導教材を公表し、学習内容を体系的かつ網羅的に整理しています。
超低金利時代、インターネットやSNS普及に伴う金融トラブルの増加、成年年齢18歳への引き下げなど、若年層であっても金融リテラシーを持っておくことが必須となっており、その教育の重要性は増しているといえます。この記事では、金融経済教育指導教材の学習内容について紹介します。
目次
金融教育(金融経済教育)の4つの分野について
金融広報中央委員会では、金融教育(金融経済教育)を以下の4つの分野に分けています。
- 生活設計・家計管理
- 金融や経済の仕組み
- 消費生活・金融トラブル防止
- キャリア教育
それぞれで学習する内容について、詳しく見ていきましょう。
生活設計・家計管理
生活設計・家計管理の分野では、以下の4つのポイントから学習を進めます。
- 資金管理と意思決定
- 貯蓄の意義と資金運用
- 生活設計
- 事故・災害・病気などへの備え
「生活設計・家計管理」は生活に関わる部分を中心に学び、社会で自立して生きていく力を基礎的な能力・知識を身につける非常に重要なパートです。「資金管理と意思決定」では、ものやお金は有限であることや限られた予算の下で、よりよい生活を築く意義などがテーマです。
また、ここではトレード・オフや機会費用など、資金管理に関する意思決定の基本についても理解を深め、実践できる技能と態度を身に付けます。
「貯蓄の意義と資産運用」では、貯蓄の意義・期間と金利の関係などの基本的な仕組みの理解を進め、貯蓄や運用に継続的に取り組む態度を身に付けます。
「生活設計」では、生活設計の必要性を理解し、将来の展望、職業選択との関係付け、生活設計のたて方について学びます。
「事故・災害・病気などへの備え」では、事故や災害、病気などの日常生活のリスク、安全を確保する方法などを理解し、実践する方法を身に付けます。
また、不測の事態に備える必要性や、備えとしての貯蓄や保険の機能を理解することもこのパートのテーマです。
金融や経済の仕組み
金融や経済の仕組みの分野では、以下の4つのポイントから学習を進めます。
- お金や金融の働き
- 経済把握
- 経済変動と経済政策
- 経済社会の諸課題
金融や経済の仕組みのテーマは、経済政策や物価など経済・金融の仕組みの理解です。
「お金や金融の働き」では、キャッシュレス・電子マネーを含めたお金の働きや役割、金融機関や中央銀行の機能・役割などについて学び、金利の働きや変動理由など基本的な金融の仕組みについて学習します。
「経済把握」は、ものやお金の流れ、家計・企業・政府などの役割、市場の働きや機能、市場経済の意義や海外経済との関係など、広範囲にわたって経済の仕組みを理解するパートです。
「経済変動と経済政策」は、景気の変動と物価、金利、株価などとの関係、景気に関する政府、中央銀行の役割などを理解することで、経済政策や景気変動が自分の生活や社会とどう関係するのかについて学びます。
「経済社会の諸課題」は、経済社会の問題点やその課題解決の理解を通じて、情報収集や合理的・主体的に考える力を身につけることがテーマです。
消費生活・金融トラブル防止
金融や経済の仕組みの分野では、以下の2つのポイントから学習を進めます。
- 自立した消費者
- 金融トラブル・多重債務
「自立した消費者」では、証紙の権利と責任、自立した消費者としての基礎知識や態度を身に付けます。
「金融トラブル・多重債務」では、金融トラブルや多重債務の実態を知り、巻き込まれないためのリスク管理や考え方を学びます。関連する法律や制度などについても理解を深めることで、対処できる知識と技能を身につけることもテーマです。
近年ではインターネットやSNSの普及により、商品・サービスのインターネットでの購買活動が主流となっていることや、成年年齢が18歳に引き下げられたことで未成熟な学生が主体的に契約を結べるようになったことなど、金融に関する状況が大きく変化しています。
「消費生活・金融トラブル防止」はこれらの状況を反映し、自立した消費者としてお金にまつわるトラブルの未然の回避や対処方法を学ぶ、重要なテーマといえるでしょう。
キャリア教育
金融や経済の仕組みの分野では、以下の4つのポイントから学習を進めます。
- 働く意義と職業選択
- 生きる意欲と活力
- 社会への感謝と貢献
「働く意志と職業選択」では、勤労の意義とお金の価値の重さを理解し、職業選択を主体的に考える力を養います。
「生きる意欲と活力」では、経済発展には付加価値の創造が必要であり、それはさまざまな人の努力によって産み出されていることを理解し、自分の夢やキャリアと結びつけることで、実現に向けて努力する力を身につけさせるのがテーマです。
「社会への感謝と貢献」では、社会とのさまざまなつながり、ルールや他人への感謝の重要性について学び、主体的に考え、行動する力を養います。
このテーマでは、自らが働くことの意義や社会とのつながりを正しく理解し、将来のキャリア形成に必要な意欲や能力を育成することが狙いです。
金融教育で使用される教材
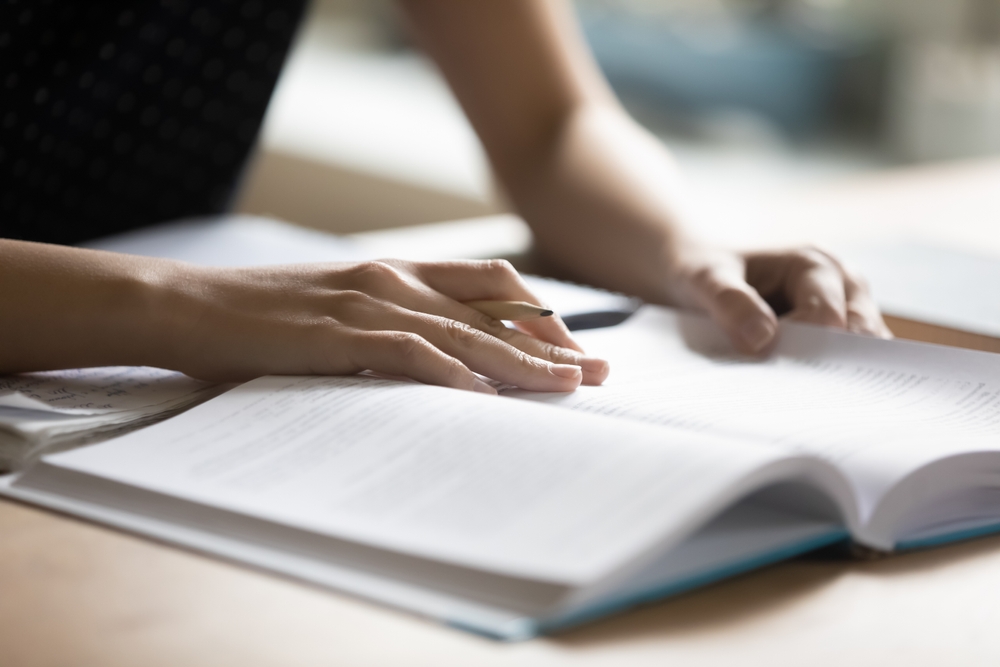
金融教育の具体的な教材として、金融庁から高校向けに「金融経済教育指導教材」が発表されています。
「金融経済教育指導教材」は以下の全7章から構成されています。
- 第1章:家計管理とライフプランニング
- 第2章:「使う」
- 第3章:「備える」
- 第4章:「貯める・増やす」
- 第5章:「借りる」
- 第6章:「金融トラブル」
- 第7章:まとめ
それぞれの項目について、具体的な学習内容を見ていきましょう。
第1章:家計管理とライフプランニング
第1章の家計管理とライフプランニングでのテーマは、主な収入・支出項目を知ることや、自分の勝利をイメージし、お金について計画することです。
家計管理では、給与をテーマに給与額と手取り収入の違い、税金や社会保険などについて理解し、家計のシミュレーションや管理の方法を学びます。また、生涯収入や支出などのライフデザインを学ぶことで、ライフプランニングの重要性や働くことの大切さについても理解します。
働き方や職業・働き方による収入の違い、人生において大きな支出を伴うイベントにどのようなものがあるかを理解してもらうことで、自身のライフプランを主体的に考えられるようになることが重要です。
第2章:「使う」
第2章の「使う」のテーマは、お金を考えてから使うクセをつける、収支をプラスにするコツを学ぶことです。お金が有限であることを理解し、必要なものと欲しいものを区別することで賢いお金の使い方を身につける力を育成します。近年一般的になっているキャッシュレスなどの見えないお金について学ぶのも、このパートです。
また貯蓄の重要性を理解し、収入と支出を計画的に管理することで貯蓄を主体的に進められる力を身に付けます。
第3章:「備える」
第3章の「備える」のテーマは、生活していく上で発生しうるリスクの備えとして、保険の仕組みや使い方について学ぶことです。社会保険・年金保険・医療保険などの公的保険の分類やそれぞれの役割、生命保険などの民間保険との違いについても理解を深め、保険の上手な選び方を身に付けます。
第4章:「貯める・増やす」
第4章の「貯める・増やす」のテーマは、資産形成の方法として金融商品や投資といった分野について、リスクとリターンの関係性などです。資産形成や自己投資の重要性、利子や金利の仕組みなどを理解します。
近年の金利が低下傾向にあることや資産形成において、投資という選択肢があること、金融商品の選び方などを学びます。
株式や投資信託、債権といった金融商品や投資の意義、リスクとリターンなどについても具体的に解説する項目となっており、将来の向けての準備をする上で重要なパートです。
第5章:「借りる」
第5章の「借りる」のテーマは、お金を借りるということの仕組みや制度、リスクなどについての知識習得です。住宅ローン・カードローンなど、商品やサービスを購入する際のローンや、クレジットカードなどの後払いの仕組みについて理解します。
第6章:「金融トラブル」
第6章の「金融トラブル」のテーマは、金融トラブルの例や対処方法について学ぶことです。2022年4月より、成年年齢が18歳に引き下げられたことで、18歳以上なら保護者の同意なしにクレジットカードを作ったり、金融商品を契約したりすることが可能になりました。
金融知識・社会経験の乏しい若年層やとくに標的となりやすく、トラブルに巻き込まれる可能性も高くなります。このパートでは、金融トラブルの事例やトラブルの回避方法、対処方法について学びます。
第7章:まとめ
第7章のまとめのテーマは、金融リテラシーは常に情報収集し継続的に行っていくことが重要であることを理解することです。
まとめ

金融教育(金融経済教育)の学習内容は、金融リテラシーの形成に必要な知識を4つの分野に分け、幅広い範囲にわたって体系的に学ぶ内容となっています。
2022年4月の成年年齢の引き下げなどもあり、資金管理や資産形成について学生時代に必要な知識を身につけることは、子どもたちにとってよりよい生活を築く上で大切なことです。
また親世代にも体系的な金融教育を受けていないという人も多く、学校現場での教育だけでなく、カリキュラムを活用した親世代との連携なども含め進めていくことが重要となるでしょう。